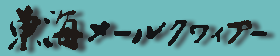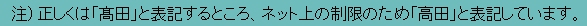『この曲は英訳すれば"Season in Heart"である。"of Heart"ではない。まして"Mental Seasons"ではない。』(高田三郎・ひたすらないのち より)
<わたしの願い>(1961年)、<水のいのち>(1964年)の2作品によって日本の合唱界に新しい時代をもたらしたといわれる高田三郎。殊に<水のいのち>の爆発的人気は、いやが上にも自作への期待を高くした。
そんな周囲の待望熱に煽られる高田ではないが、NHK名古屋から昭和42年度芸術祭参加作品の委嘱を受けた時は、密かに心に期するものがあったに違いない。というのも、その時点で手にすることが出きた吉野弘の既刊詩集3冊(「消息」、「幻・方法」、「10ワットの太陽」)に収録の64編から選んで作曲を始めたのが英語を習い始めたばかりの息子とその父の会話の中に人間の生死の不思議や哀しみを浮かび上がらせた散文詩"I was born"(1952年)だったからである。
"I was born"は吉野26歳、最初期の作品にして代表作とされる傑作詩だが、吉野は何ゆえか「この詩は作曲には全く向かないから」とその作曲をよしとしなかった。そのかわりとして提供された35編ほどの作品から高田は7編を選び構成して<水のいのち>とは全く趣きの異った混声合唱組曲(1.風が 2.みずすまし 3.流れ 4.山が 5.愛そして風 6.雪の日に 7.真昼の星)を創りあげた。それは吉野の詩に正面から向きあい深考してその詩情を汲み取り付曲した結果の事であるが、恰も、三島由紀夫が『豊穣の海』の1部<春の雪>と2部<奔馬>を2つの文体"手弱女(たおやめ)文"と"丈夫(ますらお)文"で書き分けた事を思わせる。
高田作品中で異彩を放つ<心の四季>であるが、それは高田音楽の幅の広さ、容量の大きさを示すもので、ベートーヴェンの交響曲でいえば「田園」のような存在ではないだろうか。
吉野弘と高田三郎、二人の出会いはふたりともがそれぞれに大きな恵みであった。
組曲の大題「心の四季」は、提供されたうちの1編から着想したであろう主題をもとにして高田がつけたと考えられる。日本の四季が見事に謳われているその詩を組曲の象徴として第1曲に置き、あとは春夏秋冬を構成する詩を選んで晩春から早春へと巡る季節(人生)の中に"生かされて在るいのち"、生と死を歌っている。
各曲は独立しており、<水のいのち>の様な全編を通した物語性こそ持たないが決してバラバラではない。作曲者が"in Heart"と言っているように、それぞれが生命の存在にまつわる愛の心象風景として"四季"という時の流れの下に統べられている。桜の花びらを散らす風が全編を吹き渡っているのである。「四季」は永遠に巡り巡る時間であり、そこに人生の一景が投影されていく「ひとの一生」でもある。
"風"も"時"も眼には見えないが確かに存在する生命の根源に通じるものである。心に感じる霊感とでも呼ぶべき不思議を<心の四季>は歌っている。そして終曲「真昼の星」はそれらすべてを見守る大いなるものの愛のうた。来るべき未来の曙光の中にすべての生命が生かされるようにと願う祈りのうたである。
『私は、この時の芸術祭番組を吉野さんの詩でと決めたのは、高野さんの詩集「闇を闇として」の巻末に解説を書いている吉野さんを読んでのことである。』(ひたすらないのち より) この巻末の解説とは、詩集に収録の「遡る鱒は」の読み解きによる"高野喜久雄小論"のこと。吉野はここで高野の存在論、詩人としての姿勢などを論じている。
このようにして吉野弘を知ったのだが、高田は著書の中で<心の四季>を次の様に紹介している。『私は誌の選び方にある特殊な好みを持っており、なかなか一筋縄ではいかない作品が多いが、この曲はそれらの中では取り付き易い方で「私の入門曲」という人もいる。』と...。しかしほんとうにそうだろうか?確かに吉野の詩はやさしい言葉で平明に書かれている為、読めばそれで分かった様な気になるが実は、「風合いはやさしいが生地はこわい」(北村太郎)、「どんなにやさしい言葉でかかれていても(いや、いればいるほどといってもいい)一流の作品は真の難解さを深く秘めている。」(高野喜久雄)のである。
吉野弘と高野喜久雄。詩面はいかにも対象的な二人であるが、その根本でひたすらに凝視し思索するのはおなじものなのであり、吉野弘も実は一筋縄ではいかない詩人なのだ。"取り付き易さ"は難解なイメージをやわらげる反面、内容の深さを測り損ねる危険性をも孕んでいる。そして誌の深層に届かず表面的なやさしさだけに終止する音楽では一時的な流行だけで終わってしまうだろう。しかしそうとはならずに<心の四季>がほどなく半世紀にも及ぼうかという長い歳月を多くの人に愛され歌い継がれて来たのは、音楽が誌の深みをよく表現して、歌う人聴く人の心にその都度新たな感動を呼び起こしているからに他ならない。
高田三郎は詩の深底にある難解さをそのまま炙り出すのではなく、吉野弘のやさしい表情を活かした、親しみの上に霊性を感じさせる音を選び重ねることで、そこに詩の真実を表そうとしたのではないか。音楽のやさしさだけではない特別な世界を現出させる高田三郎ならではの創造的工夫を強く感じる。
音楽評論家・宇野功芳は<心の四季>を、「曲の完成度は<水のいのち>の方が高いが内容の深さにおいては遜色なく、全篇に流れる霊的なものは<水のいのち>にはない。」(レコード芸術 2012年9月号)と評している。
1961年から1978年の間に高田三郎は芸術祭合唱コンクール(ラジオ部門)参加作品を5回書いて、芸術祭大賞(芸術祭賞)と芸術祭優秀賞(芸術祭奨励賞)を各2回、系4回受賞している。
<心の四季>は受賞を逸した唯一の曲であるが、自らの信念に従って妥協の無い仕事をした高田にとって、作品の価値は他人の評価で左右されるものではなかった。むしろ、この無冠作品に寄せられた多くの一般合唱人と聴衆の純朴な共感がその真価を証明しているのであり、作者はそれをこそ喜ぶのである。
放送初演の翌年(1968年)に混声楽譜、1970年に女声楽譜が出版されるや、先行する<水のいのち>を追うように全国的な広がりを見せた<心の四季>は初演から49年を経てなお、楽譜増刷が最多の<水のいのち>に次ぐ変らぬ高い人気を保っている。
<水のいのち>は初演から8年後(1972年)にクローバークラブの委嘱で男声版が出来たのに比べ、<心の四季>はその曲想が男性向きではないと思われたのか長い間見過ごされていた。ようやく男声版が登場したのは1994年で、今井邦男編曲・指揮、東北大学男声合唱団によって初演された。
東海メール委嘱による須賀敬一編曲版はそれから8年後の2002年10月、東海メール主催の高田三郎を追悼(3回忌)する演奏会で発表された。指揮は東の高田名人・阿部昌司。楽譜を同時出版した東海メールがこの後、須賀指揮で高松、仙台(共に2003年)と演奏を重ねたことから男声界に知られる事になり、JAMCA大分演奏会(2006年)、JCA男声合唱フェスティバル会津若松(2012年)で数百人規模の合同演奏。本年5月には歴史ある東京六大学合唱連盟演奏会でも合同演奏される等、今や男声の貴重なレパートリーとして定着している。
吉野弘は1926年(大正15年)1月16日、山形県酒田市(当時は酒田町)で役場勤務の父・末太郎と母・貞の長男として誕生、高田三郎(1913年12月18日生)より一世代若い、”雪で鍛えられた人間”を自称する北国の人である。
その時代(軍閥による政治体制化)に生きたものの宿命として成長の節々に戦争や動乱があり、中学では軍事訓練も受け、当然にようにその思想にまみれて成長した。
1938年(昭和13年)3月、小学校を総代で卒業して4月、旧制中学・酒田市立商業学校に進学する。戦時(大東亜戦争)ため1942年12月(因みに同月高田三郎は「山形民謡によるバラード」を再演指揮している)に繰上げ卒業。翌年1月、帝国石油(株)に入社した。1944年、甲種合格を望んだ徴兵検査は禁止のため不本意な第一乙種合格であった。
糸足先に南方戦線に向かった友人は乗った輸送船が途中で撃沈されて死亡。その一方で、山形歩兵第32連隊に入営が決まっていた吉野は入営予定(8月20日)の5日前に敗戦となり生き残った。19歳の夏であった。
皇国日本から主権在民の民主主義国へ。戦後の改革(1945年10月、GHQ・連合国軍司令部が「自由の指令」を発令)で会社に労働組合が結成され、その専従役員になる。
首切反対闘争などで奔走するうちに過労で倒れ、当時は不治の病と言われた肺結核を発病。右肺の胸郭成形手術(肋骨を6本切除)を受ける等1949年9月から1951年8月まで足かけ3年の入院、療養生活を送った。
敗戦直後の精神的打撃と混乱。労働組合での奔走そして肺結核闘病・治癒。敗戦と病気(3歳時の疫痢と戦後の肺結核)で通算3回死を乗り切った吉野は『病が癒えて私はつくづく生命の有難さを思い、今後は悔いのないように生きなくては』と、”生かされた”とのつ用意思いから生きることの大切さを痛感したという。そして生と死・声明は、敗戦による社会変革に厳しさから学んだ「多視点ともいうべき初の見方」や「固定概念のズレ現象」を鋭く捉えられる強い認識力をもって、現実社会、働く職場や家庭での事象の中に人間の深層・真理を透徹した明晰な理論で探っていく吉野詩の中心的主題として書き続けられる。
『僕は詩を認識だと思うんだ。』と吉野弘。事物(事象)に対する感動を端緒としてそれを曇った状態から確認と明晰の段階に高める為の作業が<詩>であるという。また『わからない或る体験が、私の詩の好箇のスタートです。わからなさを、無理に、分かろうとしません。時間をかけます。その辛抱が、表現という名の労働行為です。』とも。時間とは様々な経験の集積である。
堀口大学がほめる”折り目正しい日本語”や、志賀直哉の、文章の無類の的確さ、簡潔、男らしさを指標にしたという吉野の平明な文体はこの辛抱の結果であり、感動を明晰化する要になっている。
吉野弘の長女・奈々子がこう証言している。「よく吉野の詩の言葉遣いは平易だと評していただきます。確かに父はあえて難しい言葉を避けていたように思います。」(青土社・吉野弘全詩集増補新版あとがき より)と。
1951年10月復職。しばらくは養生しながらの半日勤務で、年が改まったころからやっと一日勤務が出来るようになった。
そんな中で詩を書きはじめ、1952年(26歳)、詩誌「詩学」に初投稿した2作品(6月<爪>、11月<I was born>)により、翌年の2月号で新人に推薦された。詩人・吉野弘の詩壇登場である。敗戦時19歳であった純真な若者が、その情熱をもって労働者の未来を民主主義本来の純粋な世界の中に切り拓こうとしていた。
『私はプロパガンディスト(伝道、宣伝者)ではないのだが、私の詩の多くはプロパガンダ的色彩を帯びている。もちろんそうではない作品も少なくはないが、見る人が見れば、私の作品の大半がプロパガンダ風のものだと見る筈だ。』(関根弘をダシに使ってのひとくさ より)
”根っからのプロレタリア出身者”を自認する吉野が詩を書き始めた初期(およそ1952〜59年頃)、労働・労働者を素材にした、いわゆる労働詩を多く書いたことから”プロレタリア詩人”とも見られている。しかしそれは決して主義、思想的な事から生まれたものではなかった。労働者の姿に見る理想と現実のギャップの、「俺は決して商品労働者にはならないぞ」との強い覚悟をもってしてもなお、耐え難い苦しみ、辛さを乗りきる為のやむにやまれぬ手段であったことを、吉野は次のように語っている。『何でこんなことを書いたのかと言いますと、要するに非常につらかったんですね。だからそういうことを確認しないと耐えられない。そういう労働者の弱さみたいなものを、自分に通知しておかないととても耐え切れない。なんとかそれをはっきり通知しておきたい。通知をしたって別に苦痛がなくなるわけじゃなくて、要するにその場しのぎでしかないわけですけれども、そういう状態で詩をつくったわけです。私は最初から文学をやろうと思って詩を書きだしたのではありません。<中略>敗戦というとてつもない事件の中で、価値の転換というのを私が非常に明瞭に見たこと。それから生命というものがとても大切なものであるにもかかわらず、資本の理論(利益追求)が優先する社会では、労働者が商品というあり方で規制されざるを得ないこと。そうした状況の中で自分を守っていくということが、私のスタートだったということです。』(私の詩の原点 より)
肺結核が治り、仕事も普通に勤務が出来るようになった1952年11月、結婚。社宅(酒田市)に住む。
翌1953年、川崎洋、茨木のり子が創刊(6月)した同人誌「櫂」に3号(9月)から参加。勤めの傍ら、詩作が本格化する。この時27歳。1954年7月長女・菜々子が生まれ、<初めての児に>(1954年)や、代表作であり中学の学習教材にも採用された<菜々子に>(1955年)がこの時に書かれている。
1957年5月、第一詩集「消息」を刊行。10月、転勤に伴い新潟県柏崎市へ転居。翌年3月、石油資源開発(株)への移籍で東京へ。中野区の寮を経て10月から板橋区の向原団地に住む。1959年6月刊行の第二詩集「幻・方法」には、戦後に書かれたもっとも美しい抒情詩のひとつとされる<夕焼け>(1958年)が収録されている。
「吉野弘は1957年、すなわち第一詩集<消息>を刊行した時点ですでに完成した詩人であった。つまりそこには詩人の相貌がはっきりとあらわれている。」(今村冬三・吉野弘の詩想 より)
霊性な認識者、認識の詩人、社会派・民衆派詩人、「戦後詩」の中の優れた思想詩人、平易な言葉で人間のありようを極めて日常的な感覚で意外なアングルからとらえてみせる不思議な人、不条理の生を静謐に生きる人間探求家、構成の詩人、戦後の詩人の中でおそらく最も優しい人格、一見平明単純でそれでいて実は手がこんでいる、貴にして重い、人間通の詩、自己に厳しく自分の卑小さのままにという男らしさ、知的論理等々様々に形容される吉野弘。
鮎川信夫や郷原宏、北村太郎、清岡卓行ら多くの詩人が「吉野弘は極めて上質、類まれな主知的抒情的資質を持った生まれついての詩人である。」と口を揃え鮎川は更に、その抒情の根源は「彼の人間性のひたむきな愛だ」と言及する。その抒情は生を凝視している。
勤めながらの詩作で、7年の間に2冊の詩集刊行は詩人としてまずは順調な歩みといえるだろう。しかしその順調と見える歩みは「理想と現実が衝突し激しく軋しむ位置に自らを置き、詩が詩として自立しつつ、しかも外部に向かって世界を劈いてゆくためにはどうしたらいいのか、という真面目な問いを抱えて歩く」(今村冬三・吉野弘の詩想 より)辛い視力を伴うものであった。
吉野弘は長いサラリーマン生活を通して、利潤追求を至上とする資本主義の下では、個という存在を侵蝕することで組織が機能して行くという現実社会の不条理、非情性を知った。そしてそれが、新フロイド主義者エーリッヒ・クロムが著書「自由からの逃走」で論じる社会的心理「人は根源的自由を扱いかねる時、それを他人まかせにし、個の自立を放棄してしまう」とが相まっての現象であることに気づいたのである。吉野は思想を思想として宣伝しようとするプロパガンダ的手法を止める。『プロパガンダは淋しい...』苦い自省が吉野に『会社も労働組合もマッピラ』と言わせた。
労働者としてではなく一般的生活者・認識者としての自己回復を果すため、詩の端緒となる、未発展でまだ曇った状態にある感動を確実と明晰の段階に高める為の認識、その自らの認識を問い直してみる必要に駆られたのである。
36歳の夏(1962年8月)、突然、吉野は19年8か月勤めた会社を、20年勤続表彰を逃れるという理由で辞めて、友人と小会社を作りコマーシャルのコピーライターに転身。週に2日勤務の自由業者を自称し、詩業との二足の草鞋で詩人としての中期(過渡期)を歩き始めた。
1964年12月、第三詩集「10ワットの太陽」を刊行する。高田三郎との出会いはこの3年後、吉野41歳のおそらく春。深刻、切実な人生体験(それは、中学入学の新学期末に母・貞を亡くした事にはじまる)から、人間の矛盾、うしろ暗さや身勝手、ごまかし、背任等々、人間の本質に通じた不惑の40代は、生命の不条理、生と死への省察を重ねながら、詩業出発時から持っていた「生かされて在る」という認識の澄明度を高めつつ、吉野弘の後期思想の核心である『欠如の思想』(生命体はすべてその内部に、それ自身だけでは完結できない「欠如」を抱いており、それを他者によって埋めるように運命づけられている)にほどなく辿りつこうとしている時期であった。
一方、高田三郎は知命(50歳)を得て、やっと自分らしい入魂の音楽がかけるようになって、名曲「水のいのち」を世に出した後の創作意欲溢れる壮年期にあった。
1967年11月、混声合唱組曲「心の四季」放送初演。組曲全7曲の詩は①<風が>を除く6編[②みずすまし③流れ(岩が)④山が⑤愛そして風⑥雪の日に⑦真昼の星(星)]が、1971年7月刊行、第23回読売文学賞を受賞した第4詩集「感傷旅行」に②⑤⑥⑦の他、「消息」に⑥、「幻・方法」に③④が各々収録されている。
後の座談会(合唱サークル・1969年6月号掲載)で、吉野は「作曲はやっぱり作曲家による詩の一つの解釈だと思うんです。」と話し、「僕はいつも詩を取違えなかったかということを心配しながら作曲しますね。」と言う高田に対し「僕の詩に関する限りはございません。」と答えている。
1972年10月(46歳)、東京での団地住まいから武蔵野の一画、埼玉県狭山市の、すぐ近くに茶畑が広がる戸建住宅に転居。雑木林が点在し、周辺には狭山丘陵がある緑豊かな自然に囲まれた環境の中で、吉野は樹木や草花に”体験できない別の生”を見つめ、その叡智を感得する事で認識を磨き詩想を深めていった。そして吉野もまた知命を得て、「生かされて在ること」と「欠けて在ること」そして「さまざまな生をあるがままの存在」、あるがままのすべての生命をそのままに受け容れて共に在る、正に静謐澄明な仏教的境地に辿りつくのである。